家の中に積み上げられた3000キロ、麻袋90袋分のコーヒー豆を前に、呉子鈺;さんの思いは複雑だ。
「一年前には言葉だけだったものが、今は『雨林珈琲』と書かれた麻袋に入って、目の前にあるのです」使命を成し遂げた達成感と、理想と現実のギャップ、それは目の前のコーヒーと同様に苦さの中に甘みを持つ。
彼が「100回生まれ変わっても飲みきれない」と言うこのコーヒー豆は4ヶ月前にインドネシアに赴き、産地価格の数%増しで直接農家に注文した最高級アラビカコーヒーだ。
今年36歳の呉子鈺;さんは、大きな目に濃い眉、1999年の台湾大地震以来切っていない髪を背中で束ねている。だが、その外見とは裏腹に子供のような繊細な心を持つ。
台湾大地震の後、彼は郷里の東勢で復興作業に参加し、4年前の大津波の後には、建築家の謝英俊氏や大隘;文化生活圏協進社の蘇詩偉幹事長といった社会運動の先輩とともにインドネシアのアチェを訪問した。この時に彼はインドネシアのことをもっと知りたいと強く思った。その後、台湾大学環境工学研究所の指導教授、於幼華教授がスマトラ北部バッカラ村の持続可能な発展計画に加わることとなり、呉さんとスマトラとの縁は深まった。
インドネシアのコーヒー生産量は年35万トン、世界第四の産地だが、スマトラではジャングルが毎年200万ヘクタールという速度で消失している。台湾での現代の消費が必要とする資源は地球の各地から来ていて、台湾29個分で支えられていることを彼は知った。自分も環境を搾取していることに気付いた彼は、インドネシアのために何かしなければ、と思った。
「身近なものとして考え、謙虚に反省しなければ、同情も理解も行動も生まれないでしょう」と言う。
現在台湾で売られているフェアトレードのコーヒーのほとんどは、西洋のディーラーから輸入したものだが、呉さんは直接産地を訪れて仕入れようと考えた。その資金を集めるために友人たちにメールを送り、可能な限り転送してもらった。目標は毎月1ポンドずつ2年間予約購入する人を400人集めることだった。結果は目標とは程遠い20人ほどだが、それでも彼は昨年12月に自らアチェ州の産地、タコンゴンを訪問し、今年6月に80万台湾ドルを払って最初の3トンを輸入したのである。
「雨林珈琲は社会的企業の路線を歩み、利益は株主に配当せず、現地の農家に還元します」と話す呉さんの計画は3段階に分けられる。まずフェアトレードから開始し、コーヒーの取引を透明化し、帳簿や利益の使途も完全に公開する。
続く「雨林計画」では、雨林珈琲の利益を熱帯雨林の回復に用いる。
すでに雨林研究計画支援の行動は始まっている。6月、彼は北スマトラ大学生物学科主任と協定を交わし、9月から教授1人に5000米ドル、研究生5人に1人500米ドルずつを提供し、熱帯雨林の基礎研究によってデータバンクを作ることになった。
「彼らがインドネシアの貧困脱出の種子になることを願っています」実は彼のコーヒーはまだ10分の1も売れていないが、この研究費は於幼華教授が出してくれたのである。
呉さんはこれを2年を1期とした一種の実験と位置づけている。2年後に計画がまだ存続していれば、さらに一歩進んで、購入と賃貸の方法で雨林回復に取り組むつもりだ。
人は夢を見るからこそ偉大なのであり、仮に失敗してもそれは美しい失敗だと呉さんは言う。
彼が最も感謝しているのは、雨林珈琲計画に賛同し注文してくれた20数名の顧客だ。その半分は転送メールを受け取った見知らぬ人である。支持者の存在こそ最大の力だ。「彼らのために、どんなに大変でも計画を貫いてみせます」と呉さんは力強く語る。
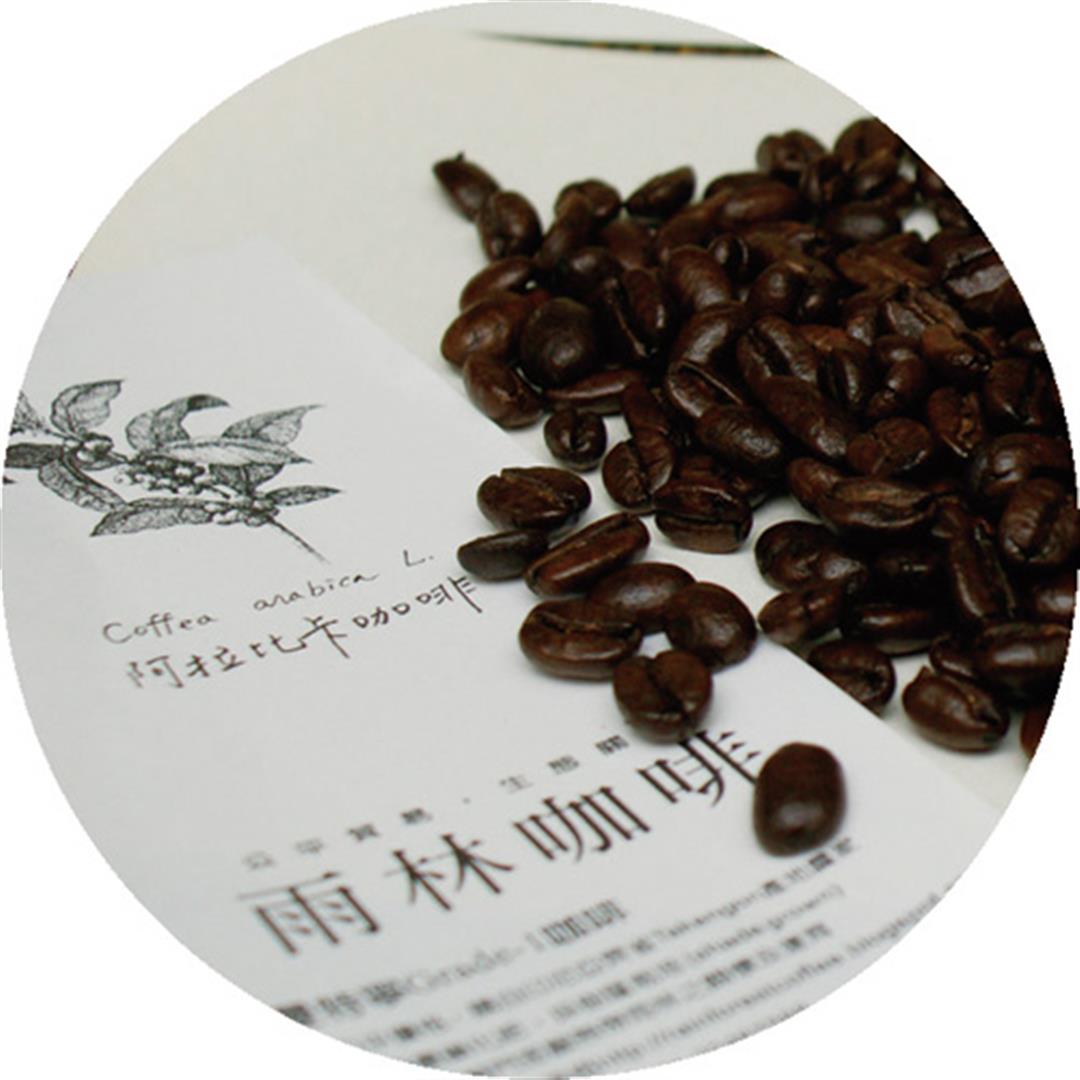
産地での注文から包装、販売まですべて一人でやる。フェアトレードを行なう「雨林珈琲」は、呉子鈺さん自身と世界を変える最初の一歩だ。