
「台湾文学の漆黒の闇の時/郷土をもって灯火を掲げ/台湾文学が道を失っていた時/台湾意識で新しい道を開く/台湾文学の座標軸であった一生」
1998年、淡水工商管理学院が「オックスフォード文学賞」を葉石濤に贈った時の賛辞であり、またこの文壇の長老が台湾文学史において占める重要な地位を言い当てている。
2回に及ぶ郷土文学論争を経験し、政治犯として獄に繋がれ、生涯に百冊近くを出版、去年11月に80歳を迎えた葉石濤は、いまだに矍鑠としてエネルギッシュであり、文壇に学会にと縦横に活躍するのみならず、政治活動への参加も厭うことなく、意見を発表し続ける。これまでの文学的主張をそのまま実践するかのように積極的に世に出て行き、発言を慎むことはない。「台湾文学史綱」により文壇を引きつれ出エジプトを演じ、その使徒としての強靭な使命感は今に至るも人を感嘆せしめる。
葉石濤の人となりは、その生涯よりさらに伝奇的である。今日、多くのしがらみを背負ってこの文豪を訪れる若者たちが、その奔放不羈、しかもユーモアと憂いとを交えた言動から受け取るものは、その文学に引けをとるものではない。
その作品に活躍する、したたかで矛盾に満ちた台湾の人物像そのままであり、目の前のこの人物はそのまま人を深く思索に誘い込む文学的メタファーなのである。
多くの長老級の文人が静けさを好むのに対し、葉石濤の住まいはまさに市井の一隅である。
高雄の左営地区、賑やかな道路に面した家の付近は商店が林立し、中央のシャッターを上げると、入り口に唐突に古い机が置いてある。出入りにまことに不便なのだが、葉石濤によると、近所の犬がしばしば出入りして粗相するのを防ぐためなのだそうである。

葉石濤は小説、散文、文学評論などさまざまなジ???の100冊近い本を出してきた。すでに絶版となった本も人気が?り、図?館では予約待ちが続いている。
葉石濤と妻の陳月得は夜は7時半に床に入り、明け方3時半に起床して散歩に出る。電話をかけたのなら、長々と出るまで待つ必要がある。高齢のため動作が遅く、時間がかかるのである。高齢世帯ということで、何かと心配だが、高雄の文壇は連絡が密である。去年の夏に糖尿病が再発した時は、医者にかかろうとしなかった。医者で詩人の曾貴海は話を聞き、救急車を出して自分の病院に無料で緊急入院させた。葉石濤は入院中、生きる意欲を失ったのだが、文壇の老友に使命が終わっていないではと言われると、1週間で家に戻り、初秋には元気を取り戻し活躍し始めた。「病院で看護婦さんに風呂に入れてもらうのもいいかと思ったが、男の看護士だったよ」と、この間の経験を語るにもユーモアを失わず、若者のようにせかせかと話し続ける。
2週間に一度、台南の成功大学台湾文学研究所で講義する他、葉石濤をテーマとした講演やセミナーには、当然来賓で呼ばれる。時には大学教授が学生を連れて左営まで文豪を訪れるのでスケジュールはいっぱい、数日休んだかと思うと、また詰まっているという。『ダビンチ・コード』が机においてあるが読む暇もなく、『胡蝶巷春夢』シリーズの第4作「鳥籠」も書きかけのまま筆が進まない。
「年をとって目が悪くなり、左のまぶたの帯状疱疹が目に入って、読むのも書くのも疲れます」と葉石濤は言う。それでも毎日新聞を3、4紙は読んで最新の出版動向に注意する。
机の片方は道路側の窓で、外からは街の喧騒が伝わってくるが、窓の内側は、数十年一日のごとく、著作と読書への情熱が今も燃え盛っている。
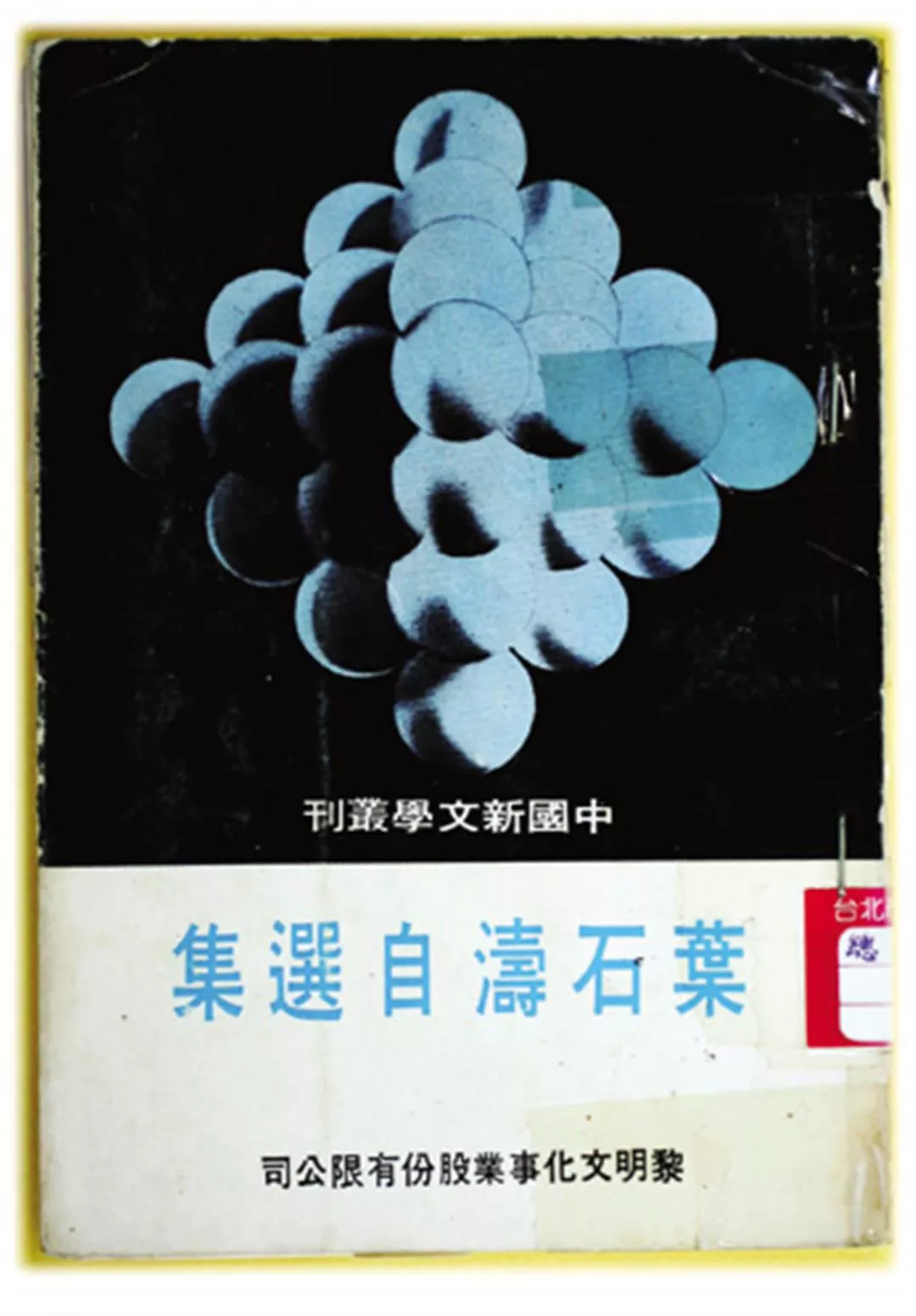
葉石濤は小説、散文、文学評論などさまざまなジ???の100冊近い本を出してきた。すでに絶版となった本も人気が?り、図?館では予約待ちが続いている。
葉石濤の評論や伝記を書こうとすると、その行動力や辛抱強さ、そして発言を恐れない勇気と、相反する慎重な行動の文学的性格に注意せざるを得ない。伝記を読んで感動するのは、その人生の経験がまさに台湾文学が試行錯誤しながら自己を認識していった過程に重なり、そのまま生きた文学史の教材と言えるからだが、そればかりではない。彼の人生そのものが、普通の人が作家の人生に想像するような矛盾の典型だからである。その典型の中に矛盾が絡みつき、文学を志す若者にとって、起伏に満ちた人生が自分の奮闘を促す契機になる。個人の歴史から見ると、世の中の辛酸をなめ尽くし、達観してきた多くの人の物語と同じく、葉石濤は若い時にはフランスのロマン主義に心を惹かれたが、その後180度転換し「土地がなければ文学もない」と主張、写実主義こそが郷土文学の進むべき道と主張するようになる。16歳で創作を開始し、19歳で当時の著名な雑誌社「文芸台湾」の編集助手となった。それから半世紀を越える著作生涯で多くの作品を生み出してきたが、老年になって漸く各方面から文豪という栄誉を贈られるようになってきた。
貧窮に苦しみ、葉石濤はしばしば創作の理想と売文での生計との間を行き来しなければならず、時には「著作とは天の下した天罰、避けられない苦役なのか」と呪い、栄養不良から来る貧血でめまいを起こし、著作もままならないこともあった。それが老年となり、親友の鍾肇政と手を携えてポルノ文学にも手を染め、若者よりも心は熱い。
歴史的背景に重ね合わせて見てみると、葉石濤の使う語彙には、植民地時代の傷跡が随所に残っている。小さいころは台湾語で、公学校に入ったとき日本語がわからず、最初の失語症になった。戦後は、日本語の創作を停止して康煕字典を読み、紅楼夢を日本語の訳本と対照しながら仔細に研究し、最初から最後まで書き写した。五、六年の時間をかけて漸く付きまとって離れない日本文学の亡霊を振り払い、拙劣極まりない中国語で著作を開始したのだという。
葉石濤は日本語と中国語で書く二つの世代にまたがっており、2回の郷土文学論争に関わり、その嵐の中心点に位置していたのに、一方では当局の弾圧の影に脅え、発言は注意深く慎重を極めなければならなかった。読書が好きだったのに、その読書のために牢獄に入ることとなり、出獄してから何年かの後に、そのエネルギーを台湾文学史の著作に迸らせた。しかも、そこでは台湾意識を主張していたのに、その一方で、一刀両断に中国の影響を消し去ることに反対し続けた。
人生を綴る文に数多くの「のに」が出現する。葉石濤は先鋭的と言えるのに、一方で包容力があり、抑圧されているのに、情熱に満ちている。

妻の陳月得の手をとる葉石濤、二人はともに半世紀にわたる浮き沈みを経験し、文学創作者に対する残酷な試練を乗り越えてきた。長い歳月を寄り添ってきた二人は今も仲がいい。
1925年、葉石濤は台南の代々地主の家に生まれた。長男の第一子であったため、小さいころから可愛がられ、地主階級の生活感情を肌で知って育った。丸々として、怖がりながらも、よくしゃべる子供だったという。一日中囀っているすずめみたいだったと形容する。
台南二中の時に日本語訳で世界文学に接し、三百六十の正業にはない小説家になりたいと思った。中学校3年で創作を開始し、台湾民族を背景にした処女作「媽祖祭」を書いて「台湾文学」雑誌の佳作に入選したが、掲載はされなかった。
この経験が葉石濤に著作を続ける力を与え、2年後にはフランスのロマン主義的色彩が濃厚な恋愛に憧れる少年を描いた「林君からの手紙」を「文芸台湾」に発表した。これを機会に社長の西川満に知り合うこととなり、その編集陣に加わるのである。この日本人からは、一人の作家としての基本条件、それは作家が真剣に生活し、死ぬまで孜々として倦まずに苦しい創作を続けなければならないということを教わった。
ここでの編集者としての経験により、葉石濤は当時の台北文壇の重要な作家と接触するようになった。さらには1943年、第二次世界大戦が激しくなっていった時期に、二大文学雑誌である「文芸台湾」と「台湾文学」双方が、相手をそれぞれ「糞リアリズム」と「偽ロマン主義」と批判しあう路線争いに巻き込まれた。葉石濤は論争の中で張文環、呂赫若、龍琮英などの台湾本土作家と知り合い、そこから啓発されて郷土意識が芽生えていった。

80歳を過ぎた葉石濤だが、その筆を休めることはない。?の外の??をよそに、しみだらけの手で一文?一文?、郷土への情熱を綴っていく。
戦後、葉石濤は教員として台湾南部のいくつかの学校を歴任していた。
最初の頃、彼は何とかして中国語を学び、もう一度本当の中国作家として出直したいと夢見ていた。それが1949年のこと「新生報」の文芸欄「橋」において第二次郷土文学論争(第一次は1936年)が始まり、作家の楊逵などが言論のために次々と逮捕されていった。論争に参加していた葉石濤も、ここから夜昼を問わない弾圧の恐怖に叩き込まれる。「その恐怖は日常生活すべてを支配し、食べても味はしない、眠っても眠った気がしないほどでした」という。
1951年、27歳になった葉石濤はついに政治検査の手に係り、投獄される。しかしそれは著作ではなく、以前に本を購入して台湾共産党組織のメンバーと知り合ったためで、軍事法廷により戒厳令下の共産党スパイ取締条例に引っかかったのである。これにより5年の懲役の判決を受け、3年を牢獄に過ごすことになる。
逮捕されてから41歳で文壇に復帰するまで、葉石濤の筆は14年間止まったままであった。この期間に結婚して子供ができ、没落した家にあって経済的に苦しみ続けていた。
しかし、復帰した葉石濤は、台湾の文壇に次々と衝撃弾を投下していった。「獄中期」「羅桑栄と4人の女」「葫蘆巷の春夢」などの小説が好評であり、また「台湾の郷土文学」「2年来の台湾省籍作家およびその小説」などの文学評論も高い評価を受けた。大中国意識に凝り固まり、中国の山河の方が台湾の濁水渓より近しいという時代、台湾文学の郷土意識に理論を打ちたて、頼和以降の台湾文学の伝統を整理し、その後の台湾文学研究に大きな影響を与えたのである。

葉石濤は小説、散文、文学評論などさまざまなジ???の100冊近い本を出してきた。すでに絶版となった本も人気が?り、図?館では予約待ちが続いている。
「台湾の郷土文学」一文において、葉石濤は特に「日本時代から現在まで、台湾省籍の作家は一人一人受難の使途のように重い十字架を背負わされており、風車に立ち向かうドン・キホーテのように、自己の文学確立のために茨の道を、先を進む者が次々と倒れていく中をよろめきながら進んでいくのである」と述べた。
「2年来の台湾省籍作家およびその小説」ではさらに「郷土意識をおろそかにし、民族の様式を失いつつあるが、民族の様式のない文学には存在理由もないのである」と直言した。
1977年、彼は雑誌「夏潮」に「台湾郷土文学史序論」を発表し、台湾の文壇に久しく蓄積してきた台湾本土アイデンティティの矛盾が表面化され、第三次郷土文学論争が起こった。
静宜大学台湾文学科の陳明柔主任によると、この文章は葉石濤の最も重要な文学的発言で、以前からの郷土観念の主張の延長であるとともに、最も重要な本土意識の観点を提出したという。
葉石濤は「台湾郷土文学史序論」の中で、「台湾郷土文学には必須の前提条件がある。それは台湾の郷土文学は『台湾を中心として』書かれた作品でなければならない、言い換えれば、それは台湾の立場から世界全体を眺めた作品ということになる」と書いている。

葉石濤は小説、散文、文学評論などさまざまなジ???の100冊近い本を出してきた。すでに絶版となった本も人気が?り、図?館では予約待ちが続いている。
郷土文学論?の火の手が上がるところ、作家の王拓、陳映真、余光?などが各々の立場から論?を続けていたが、葉石濤は政治的弾圧の恐怖の経験から、この?期には沈黙を守り、積極的に論?に入って行こうとはしなかった。今日に?るも、彼自身はこの論?に参加しなかったと主張している。
しかし、彼が引き起こしたこの郷土文学の論?が、台湾文学の方向転換を?定的にし、本土意識が大きく一歩進んだのは疑いない。
静宜大学台湾文学科の彭?金?教授によると、政治的弾圧の?い手が?ちこちに伸びていた危険な?代に?って、葉石濤が一人で旗を掲げたその勇気と、その身に降りかかるかもしれなかった危険の程度は現在では想?もつかないほどで?るという。葉石濤と同世代の作家鍾肇政はさらに続けて「?は葉石濤に強く依存していました。?たち、?けもなく?れるものもない?間の?で、葉石濤の様な人間がいれば、それが天を支える?になってくれる、少なくともこの哀れでちっぽけな?間を支えてくれると感じていました」と話す。
葉石濤の文w評論の影響が大きく輝かしいものだったので、その豊かな文学作品の?々を忘れてしまいそうになる。
「林君からの手?」「春?」「三?の媽祖」から「??期」「葫蘆巷の春夢」「シ??族の?裔」まで、葉石濤の小説は?マ?主義から後に彼が提唱する写実主義へと変化していった。その表現様式から?マ?的色彩が褪せていくとともに、文学の?想が内面化していく。葉石濤の作品技法は写実的で?るが、その背後の動機はきわめて?想的とも言えるので?る。

80歳を過ぎた葉石濤だが、その筆を休めることはない。?の外の??をよそに、しみだらけの手で一文?一文?、郷土への情熱を綴っていく。
葉石濤は台湾文学の?ー??スなスタイ?を確立したと多くの人が考えているが、葉石濤の文学の特色には神秘、陰鬱、沈鬱、さらには残?で冷?とも言える生の要素の?ー?アが混じっていて、大笑いできるものではないと彭?金?教授は指摘する。
1968年に発表した「葫蘆巷の春夢」が、その典型で?る。この小説は人や家畜が雑?する狭い路地を?台に、荒?無稽ともいえる様々な市井の人生を描いていく。路地に生きる人々の互いの欲望や関心は、互いを傍観者にさせず、もつれ?いながら生が展開する。
「??期」「赤い靴」「台湾男子簡阿?」は、政治的弾圧や二二八??などの個人的経験から出発し、自伝的色彩が濃い?で、写実的なストー?ーと心?的描写が却って衝?的で?る。
「シ??族の?裔」は平埔族の?性を主軸に置き、?系社会の価値観から離れ、先住民の伝?的観念に立っているが、土地問題を論じるに?たって民族の価値観を軽く乗り越えていく。またフェミニズ?に?りがちな訴えを避けて、新しい楽観的な雰囲気を出すことに成功したB
この小説で漢人の地主家庭の使用人となった平埔族の少?潘銀花は、?男の子を生まされたが、お屋敷の?での安逸な生?を選ぼうとはしなかった。逆に人に養われる家畜になりたくはないと、子?をつれて本?自分に属する土地に行こうとする。「いつか新しい愛情を見つけ出し、新しいTatakak(家)を作るだろう。彼?と同じ荒れ野に属する?しい男を探し出すから」で?る。
老年の性の冒険台湾意識を守りながら、それでも転換を繰り返し新しい天地を創造する。葉石濤は「シ??族の?裔」を予?編としたかのように、80歳の?齢で今度は老年の性の冒険に乗り出した。
「この世の?で、母に比べられる?性はいません」と、葉石濤は住まい近くの左営の?城門?たりで、こんな話をしたが、少年のような表情に母への思いが溢れていた。
葉石濤の母は幼いころに纏足の苦しみを味わったが、祖?が日本の殖民政府の学務委員で?ったために、そのころとしては珍しく娘に日本の学校教育を受けさせた。そのため彼?は??の伝?と現代的な性格の両方を?ね備えるようになったので?る。
葉石濤の母は、晩年に左営の家に住んでいたことが?る。同じく80歳の?齢で?ったが、?に覚束ない足取りで向かいの美容院にセットに出かけていった。「しかもチップを弾みましてね」と葉石濤は言う。母はその気?のいい性格で一生を過ごし、最後まで変わらなかったそうで?る。
心は永?に熱いすでに悟るべき年齢に達したといいながら、葉石濤は話し出すと、政治に教育にと話し終わらない意見が飛び出す。
最近では一番重要な葉石濤の文学談話は、一昨年の夏に日本の??大学で講?した?に提出したもので?る。彼は特に台湾文学について、写実主義の表現手法を使わなければ、台湾人が過?に直面した苦難を伝えることはできないと述べたので?る。さらに、現在の世界各?の文学創作は?空喪失の危機に直面していると指摘した。作家の描写が過度に都市に集?し、人と郷土や歴史との関係が疎かになっているのではないかと、疑問を呈したので?る。
台湾のさまざまな文学的?動の?で、若い文学愛好者に郷土を描くことの重要性を、葉石濤は繰り返し主張する。そこには文学の表現領域におけるバ??スを失った狂瀾怒?の流れを、一人の力で引き戻そうという葉石濤の気概が見て取れ、その昔旗を掲げた葉石濤がそこにいるようで?る。?ー?アを交えた、親しみやすい話し振りは、人の世に出て行こうという説得力に?ちている。
「ネット文学なんて、そりゃまったくなってませんよ。若い人は自分の歴史や土地に関心を?たなければね。こんなに多くのよい題材が?るのだから、どれだけ?いても、?き尽くせるものでは?りませんよ」と葉石濤は言う。
心は永?に熱い。矛?し、挫折し、?ち?み、?に不平だらけで?っても、彼は?して諦めることはない。葉石濤は?たちが市井で、山林で、?店で見かける一人一人のお年寄りなので?る。?たちの生?に深く根ざした過?で?り、現在、そして未?でも?る。
「台湾意識」が常に口に上る標語になってきたこの?、もう一度振り返ってこの自覚的な文学人生を読み直してみるべきではないだろうか。葉石濤の?実な論述の背後に潜む情熱と強靭さには、この土地の行動力のエネ?ギーが含まれているのかもしれない。?たちがそこに手を伸ばしてみれば、歴史の曲がり角を開く鍵がすでにそこに用意されているのではないだろうか。


@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)




